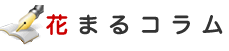『なんのために勉強するのか』 2025年10月
先日、地元・群馬県の県立中高一貫校で講演をしてきました。全国での講演活動を始めて16年ほどになりますが、関東で唯一まだ伺ったことがなかったのが群馬県でしたので、ご依頼をいただいたときには、ジグソーパズルの最後のピースがはまったような嬉しさを覚えました。花まるグループでの講演は主に受験をテーマとしていますが、小・中学校での講演では「メシが食える大人にする思春期の子育て」という演題で子育てについてお話ししています。今回は先方のご希望もあり、大学入試の最新動向や中高生の保護者にできるサポートについても触れました。
講演のなかで私は「子どもから『なんのために勉強するの?』と聞かれたら、みなさんはどう答えますか?」と問いかけました。私自身は上京志向の田舎の学生でしたので、深く考えることはありませんでしたが、中高生の年ごろになれば自然に生まれる疑問です。実は「生徒に聞かれたらどう答えればいいか」というのは私にとっても長年の宿題でしたが、最近になってようやく一つの答えにたどり着いた気がしています。もちろん正解は一つではありませんし、ややもすると大人が押しつけることにもなりかねません。本来は「なんのために勉強するのか」を自分で考えることも学びの一部でしょう。しかし、いざ聞かれたとき「自分で考えなさい」ではなく、何らかのヒントは持ち帰ってほしいと思うのは職業柄なのかもしれません。
いまの私の答えは「自分の『好き』を見つけるため」です。
中学・高校で学ぶ内容は数学・理科・社会・国語・外国語と幅広く、社会生活の基礎知識・論理的思考・表現力・文化理解など、世の中のほぼすべての領域に通じています。
数学:統計・確率・金融リテラシー・論理的思考
理科:環境・健康・テクノロジー・科学的探究心
社会:政治・経済・歴史・地理・社会構造
国語:読解力・表現力・文化理解
英語:国際的視野・異文化理解
このように多様な科目に触れることで、将来の関心や得意分野を探るきっかけになります。歴史を学べばニュースや世界情勢への理解が深まり、理科の知識は医療や環境問題など身近なテーマに結びつきます。英語は仕事や旅行、異文化交流の土台となります。つまり中高での学びは、大学に先行して幅広い教養を得られる絶好の機会であり、将来の興味や適性を探る〝カタログ〟の役割を果たしているのです。
ただし大切なのは「学び方」です。合格だけが最終的なゴールになり、暗記や作業的な学習に終始すれば、学びの本当のおもしろさやその意義を感じることはできないでしょう。「なぜ必要なのか」「社会のどこで役立つのか」という視点を持って学ぶことで、点の知識は線になり、やがて面となって世界と結びついていきます。その過程で「おもしろい」「もっと知りたい」という感情が芽生え、将来の進路選択や自己理解の土台になるのです。
その意味で「総合的な探究の時間」や「探究学習」の導入は大変意義深いことです。教科を横断してテーマを設定し、自分で調べ、考え、まとめ、発表する。覚えるだけでなく、自分なりの問いを立て、社会とのつながりを意識することで主体性とリアルさが生まれます。こうした経験は「自分の好き」や「将来やりたいこと」を見つけるきっかけとなり、たとえその時点で見つからなくても、大学進学後に改めて考えることができます。近年の大学は、学部・専攻にとらわれず学べる環境が整っており、研究領域の変更も柔軟になってきています。
ここまでの話は中学受験にも通じます。中学受験で扱う学習内容にも幅広い教養的要素が含まれているからです。いま学んでいる内容が日常や社会とどのようにつながっているのか。ご家庭でのコミュニケーションのなかで、一緒に考え、探究しながら、学びの楽しさを味わう時間がつくれたら最高だと思います。
今年もあと2か月ほどです。受験生は追い込みの時期です。不安なことは遠慮なくご相談ください。
スクールFC代表 松島伸浩