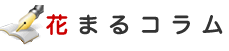『おばあちゃん、いつもありがとう』2025年12月
実家の庭に一本の大きな樫の木がありました。母屋の屋根を軽く越えるその木は、四方に枝を広げ、まるで空へ手を伸ばすかのように立っていました。私はその木が大好きでした。どこまで登れるのか、てっぺんからはどんな世界が見えるのか。小さな手で枝をつかみ、夢中で登ったあの頃。足場の不安定な枝の上で、ふと聞こえた声がありました。
「落ちたら危ないからね。気をつけてよ」
下から見上げる祖母の声でした。声を荒らげるわけでもなく、無理に止めるわけでもない。ただ心配しながら、私の気持ちをそっと受け入れてくれている、そんな温もりがありました。
高い枝の上から祖母を見下ろしました。割烹着姿でじっと私を見上げているその姿。何も言わず、ただそこにいてくれる存在。あの安心感は、大人になったいまも心の奥に静かに根を張っています。
祖母はたくさんのことを教えてくれました。草花の名前、干し柿の作り方、鎌の研ぎ方、空の色や風の匂いから天気を読むこと。祖母と過ごす時間は毎日が宝箱のようでした。そして祖母は物を本当に大切にする人でした。いただきものの包装紙を丁寧にのばして畳み、紐一本も無駄にしない。古くなった服は布巾にして油を拭く。
「まだ働いてもらおうね」
とにっこり笑う祖母の笑顔は、いまでも目に焼きついています。
なかでも忘れられないのは、ちり紙のことです。祖母はティッシュで鼻をかんだあと、それを綺麗に畳んで割烹着のポケットにしまい、乾いた頃にまた使っていました。子どもながら驚きましたが、祖母にとっては自然なことでした。
「まだ、きれいなところが残っているからね」
そう言って笑う祖母の目は、まっすぐであたたかく、どこか誇らしげでした。ものの命を見つめるように、すべてを慈しむ。それが祖母の生き方そのものでした。その姿は、私にとっての「見守る」という言葉の原型かもしれません。目の前の事象を大きな心で受け止め、手を出しすぎず、でも決して目を離さず。心地よい距離感で、相手の力を信じて待つ。あの樫の木の下で私を見上げていたまなざしと重なります。
ひとつだけ、いまも胸に残る後悔があります。保育園の遠足で動物園に行った日のこと。友達はお母さんと来ていたのに、私の隣には祖母がいました。両親は共働きで、行事に参加してくれるのは祖父母が多かったのです。私は祖母が大好きなのに、あの日は素直になれませんでした。「うちはお母さんじゃない」とむくれてしまったのです。祖母がカメラを向けても、わざと下を向き、写真に映らないようにしました。集合写真では、不機嫌な私の横に静かに立つ祖母。きっと寂しかったと思います。それでも祖母は何も言いませんでした。いまでもその話を笑いながらしてくれます。昔もいまも、どんな私もまるごと受け止めてくれる人です。
数年前、あの樫の木は切り倒されました。庭師さんも高齢になり、手入れが難しくなったのです。あの木に登った日々も、てっぺんから見た景色も、もう戻りません。けれど先日、実家に帰ると、切り株のそばから新しい芽が顔を出していました。根はまだ生きていたのです。その芽を見たとき、胸の奥がじんわりと熱くなりました。祖母の教えもまなざしも、あの樫の木の根のように、いまも私のなかに静かに息づいています。
祖母はいまも元気に暮らし、昔と変わらぬ笑顔で迎えてくれます。樫の木も祖母も、私の“根っこ”なのだと思います。どこまでも自由に枝を伸ばせたのは、深く静かに根を張る存在があったから。
そしていま、私も親となり、わが子を見守る日々のなかで実感します。つい口を出したくなること、心配が先に立つこと。「それは危ないよ」と言葉が先に出てしまい、あとから反省するばかり。「見守る」とは、その子を信じて、どっしり構えて待つことだと、後悔のたびに思い出すのです。
祖母と過ごした時間。あの樫の木と空の青さ。幼い日の後悔とあたたかな眼差し。それらすべてが、いまの私を支える“根っこ”になっています。私もまた、いつか誰かの“根っこ”になれたらと願いながら、今日も子どもたちの背中を見つめています。
花まる学習会 加藤崇彰