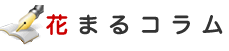『作文に書いた、卒業生の言葉』 2025年4月
毎年、2月末に小学6年道場生の卒業式をオンラインで開く。「卒業証書」を授与し、私たちから感謝と激励の言葉を贈り、子どもたちは道場での思い出を語り、作文に書く。作文には子どもたちの思いが綴られている。
■ I・Sさん 「6年生の努力」
1年生から花まる学習会に通い、4年生の春にスクールFCに移り、その冬、なんとなく中学受験をしようと思い、受験コースに進んだ。そして、学習道場には5年生の夏にやってきた。
「『うそ』という言葉が合うくらい課題をやっていなかった。その状態が(5年の)7月から3月まで続いた。6年生になり、課題をやらなくてはいけないと思っても『1ℓのうちの1dl』くらいしかしていなかった。夏期講習は最悪だった。授業は毎日あるし、課題もあった。いやで、いやで時々抜けることもあった。6年生の秋、さすがにやらなくてはいけないと思い、毎週金曜日の自学室に出て勉強した。」
成長期による身体の不調で休むこともあって、彼は学習量が少ない。6年生の、秋も深まる頃から彼の本気の取り組みは見られるようになったが、まだ実力は途上、希望するK中学校に合格するまでには時間が足りない、厳しいのかもしれない。それでも受験校を変えず、K中学校だけに絞った。
2月1日、試験場に入る直前にオンラインで受験生を応援する。初めての受験に緊張してかしこまる表情を見せる子が多いなか、彼は合格を信じきって自信に満ち「行ってきまーす!」と飛び切り明るく元気に試験場に入っていった。彼の楽観はどこからくるのだろう? 不合格も十分あり得る。確信が打ち砕かれたときの落胆を心配したが、杞憂だった。1回目の受験でK中学校の合格を決め、彼の受験は終了した。
作文には「あんがいあっけなかったな」と書き、タイトルは「6年生の努力」だった。
■ О・Iさん 「あきらめない」
他塾に通っていたが「いやになって」、学習道場に来た。学習環境が変わってもすぐに好転することはなく、課題は「ずっとやっても終わらない」状態だった。特に算数の問題解法を理解、定着させるまでには繰り返しが必要なうえ、間違えを恐れるあまり慎重になりすぎて考えることを中断するなど時間がかかる。
「6年生になってから自習室に来るようになりました。だけど、勉強している時間よりボーっとしている時間の方が多かったです。12月ぐらいになってもっとがんばんなきゃと思いはじめました。それで毎日、自学室に入って質問をするようになりました。」
自ら質問するようになってから、わからないことがわかる、できないことができるようになって、少し変わってきた。正直でまじめな子なので、時間はかかっても一つひとつ、わかることできることを増やした。「国語があまり解けなかったけれど算数はたくさん解けました」と入試の感想を書いていた。希望する学校は基本を重視する問題傾向ではあったが、算数の苦手な彼女が「たくさん解けた」ことは、努力の成果になった。
「4、5年生に伝えたいことは、あきらめないでやればできるということです」と結んだ。
■ I・Aさん 「お母さんの言葉」
「野球観戦の帰りに(親と)中学受験の話になったとき、何も考えず『受験をやる!!』とぼくは言った」
こう作文を書きだす。学習道場に入り受験学習をはじめたが、「何も考えず作業的にすすめ」、「6年の夏から何とか宿題をがんばったが、質問ができなかった」という程度の学習で、主体的に取り組んではいなかった。担当者から「あなたは受験生ではない」と叱咤激励されても、課題を出さず、クラスを替えられ、もう受験をやめたいと思った。しかし、本当にやめてもいいのかと見つめ直し「もうあと受験まで4か月だから、本気を出さなくちゃ」と奮起した。
「初めての受験は第一志望のH中学校、ぼくは少しも緊張しませんでした。なぜかというと、お母さんが『もし不合格でも、勉強した事実は変わらないから安心して』とぼくをはげましの言葉で送り出してくれたからです。手ごたえはあったものの、残念ながら不合格でした。ぼくは『あー落ちちゃったかー』と。僕はお母さんの言葉があったので、そこまで落ち込みませんでした。2回目のH中学の受験は、正直、1回目の受験より面接以外は手ごたえがありませんでした。だけど、ぼくがやっているボーイスカウトのことを話せて、とても満足のいく面接でした。そして、結果待ちで、そわそわしていると、お母さんが『これで、あなたをとらなかったらH中学が損するよ』と言ってくれました。」
2回目の受験で彼は合格する。彼の作文の題名は「お母さんの言葉」だった。
西郡学習道場代表 西郡文啓