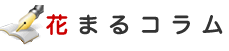『ノブレス・オブリージュ』2025年7・8月
私はいまこの元気なうちに、花まるグループのかじ取りを次世代に譲らねばということで、さまざまな手を打っています。私の思いとアイデアと直観を信じて、応援して口コミで広げてくださるお母さま方の力に頼って、ひたすら毎日の授業と手作り経営に熱中していたらいつの間にか拡大したという、典型的な中小オーナー企業の道を歩んできたので、新時代の組織改革のために入ってもらった経営の専門家のお話は新鮮で学ぶことだらけです。
そのなかに広報でお手伝いしようという方がいて、素直にアドバイスを受け入れて記者レクチャーというものをやってみました。要は、専門家として30年以上まい進してきた経験と知識と課題を観る目があり、新聞などの記者の方々に参考になるレクチャーができるのだからやりなさい、というものでした。「記者のみなさまに集まってもらうなんて、そんなことできるのかな」と半信半疑で日程を決め当日を迎えたのですが、名だたる大手新聞各社に、有名な雑誌やウェブメディア、本をつくる出版の方々など、オンライン込みで20名以上が集まってくれました。
子育ての講演会ならば自信がありますが、まったく趣旨の異なる情報提供の場ということで久しぶりに緊張して、自分としては最高度の集中力で7〜8時間の準備をして臨みました。与えられた時間が40分間だったので、前半は「現代の教育界での課題」として、列挙する形で課題を示しその背景や問題の本質・あるべき対策案などを次々に解説しました。不登校・オンライン学習・教育とエビデンス・親教育・中核的概念・ギフテッド教育・父の役割・母の役割・非認知能力・障がい児教育・英語・AI時代の教育・野外体験・始動力・学力の図解(基礎・思考力・べき力・ハカセ力・心)・探求学習・自分の考えを述べる態度の低さ・幸せに生きる力・大学基礎研究の先細りと民間依存の光と影・発達障がい対応・公教育の解体的出直し等々です。
後半は、その中で「不登校」に絞って、原因やあるべき対策などを詳しく解説しました。理屈ではなく、「これで良いのではないか」と直観したらすぐに行動に移してきたので、現場の事例と見解はたくさん話せます。不登校については、そもそも学校には行けなくても花まる学習会やスクールFC、西郡学習道場、シグマTECH、アノネ音楽教室には通えている子もいるのですが、専門の機関もつくっています。一つは南浦和に本部を置く「Flos(NPO子育て応援隊むぎぐみ所属)」で、25年以上臨床心理士たちが、障がいやさまざまな知や心の課題を持つ子たちへのカウンセリングや学習指導をおこなってきました。ここ一年の実績だけでも38名の不登校系の課題を持つ子たちが通い、カウンセリング等の地道な対応によって、34名(約9割)が登校復帰または学校復帰途中という結果につながっているという報告書を配付して解説しました。もう一つはすでに大きく注目されていて出版の依頼も来ている、吉祥寺の「花まるエレメンタリースクール」。「もう一つの学校」として、公教育を補完する形で3年間発展してきました。出席率・在籍率の高さは間違いなく日本一で先頭を走っているので、誇りをもって説明できました。
事後の記者のみなさまの反応もすこぶる良く、これから「教育の現場に立つ者」として定期的に発信していきたいです。
さて、発表事項をまとめながら考えたことがあります。わざわざNPOを立ち上げてまでなぜ障がい児教育を継続してきたのかを、客観的に眺めることができたのです。心理士の人件費は高いし在籍継続率も不安定で、たったの一年も黒字になったことがありません。なぜ続けたのか。それは、私の気質のせいだとわかったのです。経済的に成立するのは難しい。しかし、わが子にどうしてあげれば良いのか見極めきれず、困っている親御さんが間違いなくいるならば、「俺がやるしかないだろう」という、うぬぼれや思い込みに近い感情です。
野外体験なども典型的ですが、ケガ等のリスクはあるわけで、経済合理性だけで判断すれば「何かあったらどうする」という視点から回避するのが妥当でしょう。しかし、知力・健康・体力・人間力等々あらゆる面から見て大自然のなかでの自由遊びほど子どもの成長に大事なことはないと信じるならば、俺がやるしかないと思い込んでしまう自分がいるということです。
ノブレス・オブリージュという言葉があります。高い社会的地位には義務が伴うという意味のフランス語で、旧制中学系の地方進学校などに残る文化だと見ているのですが、自分自身もやはり旧制熊本中学にルーツを持つ熊本高校出身なので、「この男にもその文化は根付いているのだな」と、まるで他人事のように見えたのでした。
ここまで書いてきて、自分をやや美化した感じもしてきました。本音では競争と言ったらなんとしても負けたくない自分がいるし、公共心を持って頑張った結果、儲かるのなら儲けたいという欲ももちろんあるし、甘い誘いに弱い凡人であり続けました。ただ、育った環境のおかげで、少しだけそういう気質がしみ込んでいることも確かで、これは今後の花まるグループの芯として次世代にも受け継いでほしいなと考えています。
その一つでもあるのですが、2年前のグループ30周年を機に「花まる・伸生育英財団」という財団を立ち上げました。「お金が足りなくて、有為な若者が受けるべき教育を受けられない」ということは、社会全体で忌避すべきこと。花まるグループとしても公共奉仕の意味で、細々ですが大学生に絞って月2万円の給付型奨学金を出しはじめています。いまのところ「日本国内の大学に在籍し、福祉・保育・教育の学部学科で修学する大学二年生以上」が対象です。9月に向けて追加で若干名も募集していますので、卒業生やお近くの学生などにそのような支援があると助かるという若者がいたら、ご応募ください。応募条件がありますので、まずは以下の公式サイトでご確認ください。
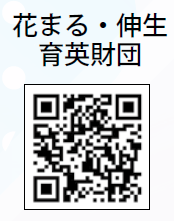
さあ、夏休み。子どもたちにとっては、ただ一度のその学年の夏です。野外体験・自由研究・読書・家族の思い出作り……。それぞれの関心に従って、子どもたちに多くの体験を。そして瞳が輝く夏でありますように!
花まる学習会代表 高濱正伸