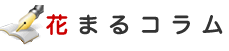『「みて!」「みる!」』2025年4月
「私自身、図工に苦手意識があって上手に導けないので、Rinせんせいの教室に連れてきました」「ほめ方や認め方を、私が学びたいんです」保護者の方にそう言われることがよくあります。
日々子どもたちがつくる作品を目にして、「上手だね」「それはなに?」といった言葉しかかけられていなかった、と苦笑いしながら教えてくださる保育士さんやお母さんもいます。
最近、ある保育園で保護者向けに記録していた授業中の動画を見返す機会がありました。その映像には、子どもたちの創作の様子や、わたしとのやり取りが収められていました。
「赤い色がここについた!」「すごい色になってきた……」「見て! 黒になった!」
子どもたちは、「聞いてほしい、見てほしい」と言わんばかりに生き生きとした声をあげています。そのなかで、私はどんな言葉をかけていたのだろう、と改めて動画を確認し、あることに気づきました。
私は、彼らの息づかいが感じられるすぐそばで、ただ見守っていました。なにかをさせようとも、止めようともせず、なにも声をかけていませんでした。
彼ら自身の言葉が、内面から自然に出てくる瞬間までは。
いちばんの発見は、「見て!」という言葉に対して瞬時に「見る!」と返していたことです。「なあに?」でも「見てるよ!」でもなく、ただ「見る!」。きっと彼らがほしいものは、「あなたのことを知りたいんだよ」という私の想いだけなのだ、とでもいうように。
そもそも表現活動に、上手い下手はない。正解に向かうこと、上手であること、を求めるのをやめると、子どもたちは自分がいま最も関心のあることに向かって、自由に探求し、没頭し、驚くほどの集中力のままに自らを表現します。
さらに、「なにかであること」を求めるのをやめると、その質感や色彩の魅力、形態のおもしろさに目がいきます。
「なにか伝えたいことはありますか?」「これはどうやってくっつけたの?」と制作のプロセスについて質問することで、子どもたちからの主体的なプレゼンテーションがはじまりますよ、と書籍ではお話ししてきました。
しかし実際には、私が最も集中していたのは、その子の作品もそうですが、その子の“こころのありよう”でした。ただ自分のこころを寄り添わせて、こころから共感していただけだったのだと思います。
先日、10年以上前の教え子が「いちばん覚えている先生は誰?」という質問に私の名前を挙げてくれたそうです。幼児期に教えた子どもたちは、いちばん大変だった(それは大人の勝手な感想ですが笑)頃のことはすっかり忘れて、大抵は受験時代の先生のことをよく覚えているものです。でも、それが当たり前です。彼が、「見えている」タイプの子だったのでしょう。
「丸ごと受け止めてくれる先生だった」「最高だった」そんなふうに言ってもらえて、私の鼻の穴は膨らみました。意気揚々と「見て!」を伝えてくる子どもたちと同じように。
井岡 由実(Rin)