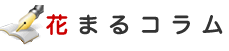『書くことは、自分を生きること』2025年7・8月
伝えたいことがあって、書く。表現の一つとして、書く。頭や心を整理するために、書く。文字にして残し、情報を正しく伝えるために、書く。将来の自分のために、書き残す。メールやLINEの返信を、書く。肉筆で届けたい思いがあって、手紙を書く。日常には書く場面が本当にたくさんあります。
物を書くことは五本の指に入るくらいに好きな私も、やる気がおこらないときがあります。それは、「must」になった瞬間です。やらねばならないもの、になったとき、モチベーションが下がったという経験は誰しもあるのではないでしょうか。「よし、自分のためにこれは書き残そう」と思って書くときと、「出しなさいと言われたから書く」ときとでは、集中力も、意識の深さもまるで違います。
幼い頃、人からやりなさいと言われたことをやることに抵抗がある子どもでした。「やりましょう」「ハイ!」とはいかず、立ち止まってしまう。いまふり返ればそれは、「自分がやりたいと思えることかどうか」にとても忠実で、正直であったのでしょう。むしろそれは、悪いことではなかったのです。
大人にとっては、仕事もそうでしょう。どんな業務にも、意味や目的、おもしろみややりがいを見つけ出すことができるかどうかというのは、やるなら「must」ではなく「want to」で、という視点でしょう。
ちなみに、世の中で最も主体的な仕事をしているのは、芸術家だと思います。なぜなら、何かをやらされているアーティストなどいないから。
作文も学習も同じです。「書きなさいと言われたから」「“上手な作文”を書かなきゃいけない」と思いながら書くほどつまらないことはありません。そういう子たちは総じて、とても気持ちの優しい良い子なのですが、「書く喜び(want to)」をまだ知らないのです。
「上手な作文」って何でしょう。それは形式や体裁ではないのです。つたなくても人の心を動かす文章はいつでも、“自分の言葉”があふれ出ている、つぶやきのようなもの。
子どもたちに伝えたいのは、書く楽しさです。「書かなければならないもの」ではなく、「書きたいもの」となったとき、子どもたちの創造の羽がはばたき、自由自在に書く力をつかんでいく。
大人になり、何か目的を持ち「書きたい」と思ったそのときに「自由自在に」「自分の言葉で」書ける人になっていきます。
文章を書くということそれ自体を、楽しい、おもしろいと思い、気持ちを表現したらすっきりする、というような感覚を、学習の最初の時期に持たせてあげること。
低学年までに「文を書くことのおもしろさ」を知った子たちは、高学年以降、自分の思いを人に伝えるためだけではなく、人と違う自分というものと対峙するときに、言葉という武器を使って自己対話し、思考を深めることができる人になっていくからです。
「ありがとう」と「だいすき」であふれる、手紙の贈り物。文字を書きはじめたばかりの子どもたちがくれる文はいつも決まっている(たいていひっくり返り文字があって、それすら愛おしい)。
伝えたい言葉があるのは、生きている証。そこには人が社会的な生き物として存在するときの根源的な欲求が存在していて、私はいつも感動する。
彼らはすでに知っているのだ。私たちは「愛」と「感謝」を人に伝えたくて生きている。
井岡 由実(Rin)