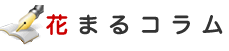『わからないときに踏みとどまれる力――深い安心はどこにあるのか』2025年10月
「幼児期に非認知能力を形成することは重要だ」ということは世間でも知られていることです。
そして誰しもが、「わが子に自分らしい人生を選んで、幸せになってほしい」と願っているでしょう。
ではいったい、私たち大人がどうあれば、子どもたちが学ぶ意欲をもち、自分らしさを大切にできる人になっていくのでしょうか。
子どもたちを見ていて、「伸びる子と伸びない子の違いはなに?」と問われれば、それは「わからないところで、踏みとどまり、考え続けられるかどうか」にあると感じます。
わかったときの喜びを知っていて、答えを先に言われたらつまらない、と思っている子は、「自分で考えたいからヒント言わないで」と言い、「もっと難しい問題やる?」と聞いたときに「やるやる!」と答えます。
彼らは、「正解かどうか」で評価されるのではなく「挑戦したこと、考えたそのプロセス」をいつも讃えられた子たちです。「わかった!」ときの楽しさを、「発見した!」ときの喜びを、「感動した!」ことの共感を、たくさん味わっているかどうか、です。
なぜアートを通して非認知能力(自尊心や向上心、結果として学びへの意欲)を高めることができるのか。
それは、創作は自己決定の連続であり、その先にある作品(自分自身)を丸ごと認めてもらうことの繰り返しだから。
花まるの年中・年長コースで最も大切にしていることと同じです。
自分の個性を強みとしてポジティブに捉えたり、ほかの子のいいところを見つけて、相手を見下したりするのではなくお互いを対等な関係として認め合っていくには、「必ず自分のなかに答えはあって、それを大切なものとして扱ってもらえた」という体感、「自分は自分で良いのだ」と思える感覚が必要です。
幼児期に、「自分はOKだ」と信じられる感覚を身につけておくと、将来何かのトラブルやストレスがあったとしても、粘り強く対応することができるのです。
私自身が幼児期に、「少し変わっている私の性質を否定されなかった、応援してもらえた」と捉えられたある出来事について、お話しする機会がありました(※)。実はそのエピソードは、母から聞いた話でも、自分が覚えていた話でもありません。母の直筆で残された幼いわたしへの眼差しや、ときに反省、おもしろエピソードが書きとめられた園時代の連絡帳が、教えてくれたことでした。
自分とは何者か。そんな問いを見つめる頃にひとりでよくやっていた習慣。それは、幼い頃の写真アルバムと連絡帳を見返すことでした。床に座り込んで大きなアルバムのページをめくり母の字を読む。私は何を確かめたかったのだろうか。
赤裸々に綴られた、母と当時の先生の、連絡帳を介したそれぞれの自己対話の跡。それは大人も不完全な一個の人間であって、書く行為を通して人は考えるものなのだ、という、当たり前だけれど大切な、人生における羅針盤を授かっていたのだといまならわかります。
覚えていなくても、自分がどれだけ愛されてきたのかが実感できる。思春期の私にとって、それらは心のよりどころだったのでしょう。
子どもたちにとって、「自分には居場所がある」という深い安心感をもたらすものは、もしかしたら過去にすでにあるものなのかもしれません。
人生における「わからないこと」に立ち向かうときに、自分で決めたことを信じ、踏みとどまって考え続けられるかどうかは、「わたしは愛されていた」という深い実感の上にあるように思うのです。
井岡 由実(Rin)