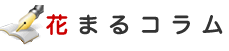『脳裏から離れぬ子』2012年2月
これまでに数多くの子どもたちと学習してきた。その一人ひとりが私の財産であり、今の私を作っている。伸びてくれた、結果を出してくれた、合格してくれた、預かった責任を果たして時は安堵するだけだが、結果として何も出来なかっ子どもたちは、どこか脳裏の片隅にいて、ときどき、ふと表に出てくる。
学生の頃、教師の見習いをやった。赴いた学校は地方都市の繁華街を校区に持つ小学校で、その学校の小学2年生のクラスで実習を経験した。そのクラスに、痩せて小柄、皮膚は荒れ、みるからに心身の発達が遅れている子がいた。母親と祖母、そして兄か姉とで暮らしていた。母はその繁華街でホステスとして働いて、夜遅く帰宅、子どもの学校に行く時間はまだ寝ている。祖母が面倒をみているが、彼の身なり体格からすると、祖母だけでは世話が行き届かず、食事も十分にとれていないようだった。どんな子どもでも喜怒哀楽の表情をこぼす瞬間があるのだが、彼にはない。表情はない。そして一言もしゃべらない。担任から彼の境遇を聞かされ、そして、あの子と話が出来たら一人前の教師だよ、と言われた。
若い私は、そんな子どもなら尚更話してみせるといきがったが、何を話しかけても、彼は一言も話さず、むしろ無視するようにさえなってくる。物言わぬだけに、無表情なだけに、私を見透かしているように思え、次第に、私自身の傲慢さ、思い上がりを思い知らされることになった。自分のやっている彼への言動すべてが偽善的に、彼から映し出される。見習いが終わり、その学校から離れるときには、ただただ敗北感、何も出来なかった自分を知ることになった。
スクールFCを南浦和に開講した当初、一階下にメンタルクリニックがあった。今の南浦和本部の事務所がある階だ。クリニックの医師は高校の同窓生であり、頻繁に情報交換をしていた。むしろ不登校をはじめ、精神的な発達障害について彼からいろいろ教えてもらっていた。ある時、その医師から電話があり下に来てくれと呼ばれ、そこで中学3年生の保護者を紹介された。両親とも学校の先生で、父親は寡黙で多くを語らず、母親はさばけた感じで、その中学3年生の娘のことを初対面の私に学校の先生と塾の講師との隔たりなく、気さくによく話してくれた。 その子は当時不登校で学校に行っていない。中学1年のときにいじめにあい学校に行かなくなった。両親の話だと学校を提訴するほどのいじめではなく、同級生の些細な言動を深刻に受け止め思い込み、批判や無視を級友が行っていると思い込んでいるらしかった。クラスメイトの誘いで何度か登校を試みたが、結局、二日と通うことはなかった。両親がメンタルクリニックに相談にきて、治療を開始、同時に学校への復帰が叶ったとき学業の不安が少なくなるように学習面をフォローしてほしいと私のところにきたのだった。
彼女との個別授業は週一回、昼間に行った。授業といっても最初は何も教えず、話を聞き出すことだけに終始し、まずは通ってもらうこと、心を通わすことだけに専念した。あなたの敵ではない、あなたを追い詰めたりはしない、ただ、一人でもあなたと話す相手がこの世にいることがわかってくれればいい。しかし、こちらが話しても多くを語らず、だからといって執拗にこちらだけ話しても逆効果、押し付けや強制、頑張りは禁物。しかし、何の会話もない間もまた相手を圧迫する。焦るな。あなたがどうにでも好きにすればいいよ、話したいときに話せばいいよ、という態度をとりつつ、ぽつりぽつりと話しかけ、沈黙の間が圧迫にならないように、こちらがつとめてリラックスした雰囲気をつくり出した。
彼女の冷めた表情は崩れないが、私の問いに断片的ながら 次第に答えるようになった。いじめの核心部分は言わなかったが、級友から心無いことを言われたこと、昼と夜が逆転し朝まで眠れないこと、そんなときは小説を読んでいることなどを話すようになった。彼女が口に、表に出すかぎりのいじめ、それ自体はよくあることだった。生きている上でその程度の言葉はよく浴びせられる。しかし、その程度とは決して言わず、私自身、心無い人から浴びた言葉で傷ついたこともあることを婉曲的にオブラートに包んで並べ、距離を縮めようと努めた。過敏で純粋、彼女らの持つ一面でもある。人間関係、そこには欺瞞もある。聖ではなく俗。所詮、人は自分中心で生きている。あなたが思うほど相手は思っていない、何も思いつめることはない、聞き流せ、とは年を経て開き直ることなのか。その時の彼女にその言葉は通じなかった。
しかし、時が経つと、僅かではあるが徐々に学校の学習に取り組めるようになった。今の学校から離れて高校に入れば人間関係も変わってくる、また違う自分が生まれる。高校という響きになんとか興味を示しだした。そして彼女は県立の定時制高校に合格し、通うことになった。定時制高校へ進学という選択は、彼女にいい結果をもたらすと期待した。定時制高校には、年齢、境遇、職業の違う、様々な人がいる。彼女の視野も広がるだろう。枠から外れても生きていけると。
それから数年後。同級生でもある医師が悲痛な表情で、あの子、自殺した、と私に告げた。返す言葉がでない。教えることに何の意味があるのか。学校に通わせることを目標に学習したことは、彼女を解放するどころか苦痛を助長したに過ぎなかった。学校なんてどうでもいい、生きていれば、なんとかなる。後悔してもただ空虚。虚しさだけが残った。
今、私は、預かったその子ために私に何が出来るのか、既成概念を取り払って考える、と決めている。